ADHDの私は注意散漫になりがちで、物を置いた場所をすぐ忘れて、日々の生活の中で「あれ?あれどこいった?」と探し物ばかりしていました。
片付けが苦手で、散らかり放題の部屋でため息をついて、そんな時間の積み重ねで自己嫌悪に陥る。
そこで「モノの住所を決める」という行動実験をしてみました。これは言い換えれば、「すべてのモノの居場所を明確にする」ということです。その効果をお伝えします。
モノの住所を決めるってどういうこと?
モノの住所を決めるとは、「特定のアイテムを特定の場所に置くルールを作る」ということ。たとえば、ペンは「机の引き出しの右端」、イヤホンは「バッグの内ポケット」という具合に、あらかじめ「これはここに置く」と決めてしまうことです。
住所を決めるメリット
探す時間が激減
「あのイヤホンどこだっけ?」と焦る時間が減ります。住所を決めた場所に戻す癖をつければ、「そこを見ればある!」という安心感が生まれます。
決断疲れが軽減
モノの住所を決めることで、「これはどこに置こう?」という日々の小さな決断が減り、脳のエネルギーを節約できます。ADHDの私は、毎日の決断に疲れやすいので、大きな助けになります。
片付けのハードルが下がる
「とりあえずそこに戻す」というルールがあれば、片付けがスムーズになります。完璧に整理整頓しなくても、「住所に戻すだけ」と思えば気が楽です。
余計なものを買わなくなる
モノの住所を決める習慣が身に付くと、住所に入りらないモノの処分に大きなストレスを感じるようになります。
そうなると、新規でモノを買う際に、
置き場はあるか?
今あるモノを処分する手間をかけてまでこれが欲しい?
そもそも、本当にこれは必要?
と、自問自答するようになり、衝動買いがなくなります。
モノの住所を決めるコツ
シンプルで手間がかからない場所にする
「戻すのが面倒」は大敵です!
生活の導線を考えた場所に住所を作りましょう。
小さなエリアから始める
いきなり家全体を整理しようとすると挫折しやすいです。
まずは「文房具」「カバンの中」「キッチンの引き出し」など、小さなエリアからスタートします。
そのうちに、意識せずとも住所を決める癖がつくようになります。
頻度に応じて住所を決める
毎日使うものはすぐ手に取れる場所、
月に一度しか使わないものはクローゼットの奥、
といった具合に、使用頻度を考慮して配置を決めましょう。
所在地のキャパを超えたら取捨選択をする
ぎゅうぎゅうに服が詰まったクローゼットに服を戻す。
何層にも皿が積みあがった食器棚に皿を戻す。
積み上げたり、詰め込んだり。その作業にめんどくささを感じるようになります。
この「めんどくさいなぁ」は本当に侮れません。
次第にモノを適当に置きっぱなしにしてしまいます。
そして気が付けばまた部屋が散らかり始めるという悪循環を招きます。
「キャパを超えたら取捨選択をする」ことを意識しましょう。
住所に入りきらないモノが出てきたら、それは必要以上にモノを持っているサインです。
おわりに
「モノの住所を決める」というのは、片付けが得意な人には当たり前のようですが、ADHDの私にとっては生活をガラリと変える大きなきっかけになりました。何度も忘れたり、散らかったり、紆余曲折していますが、以前とは違って生活が楽になり、片付けに関して自己嫌悪に陥ることは減りました。あなたの暮らしが少しでも楽になるヒントになれば嬉しいです。


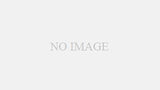
コメント